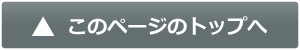巻頭言
更新版グローバル・スタンダードの採択から5年
~より包摂的な社会福祉教育の未来に向けて~
日本社会福祉教育学会 理事 Virág Viktor(日本社会事業大学)

(日本社会事業大学)
国際ソーシャルワーク学校連盟(IASSW)と国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)のそれぞれの総会が、2020年の6月・7月に『ソーシャルワーク教育・養成のためのグローバル・スタンダード』(IASSW・IFSW,2020)の更新版を承認してから、今月をもってちょうど5年が経つ。日本でも、この5年間の間に資格者養成カリキュラムの見直しが行われた。この機会に、両者の比較からみえてくる将来的な社会福祉教育への示唆を模索したい。網羅的な比較よりも、特に本質的な課題の抽出と、それらを踏まえてこれから期待される方向性に焦点を当てる。
更新版グローバル・スタンダードが示す諸基準は、世界中の社会福祉教育の発展段階や各国・各地の文化等のローカルな文脈に考慮して、必須的(全校が遵守すべき)ものと、発展的(可能な場合に充足すべき)ものを含む。例えば、『養成校』については、日本の現状は必須的基準を満たしているといえる。しかし、「カリキュラム」の全般に関する発展的基準においては、日本社会の中に実際に存在する文化等の多様性を反映できていない不十分な点も見受けられる。これは、「コア・カリキュラム」についても同様で、このような多様性の他に、グローバルな課題や自然災害以外の環境問題に関する内容が一般的に不足している。また、「実習教育」に関する必須的基準がほぼ満たされているが、実習における周縁化された当事者学生の包摂や合理的な配慮について悩んでいる学校も少なくなかろう。さらに、実習に関する発展的基準は、日本では3つともなかなか満たされにくいままある。具体的には、これらの基準が教育課程の総時間数(日本では1,200時間)の25%(日本では300時間)以上として定めている実習時間の他に、実習に関する様々な意思決定や学生評価などにおける利用者参加、また国際的な実習配属の可能性を巡る問題がある。
次に、『人々』の領域についていえば、「教育者」に関する必須的基準である、多様性に考慮した本格的な採用方針を表明している養成校はかなり少数であろう。同じく、「学生」については、入学基準等における利用者参加と、文化等の多様性に関する自己覚知の機会提供という、2つの必須的基準の充足が問われている。そして、必ずしも満たされていない発展的基準として、サービスが行き届いていないマイノリティーグループ出身の学生の包摂(入学等)に向けた積極的な措置と、教育の運営・実施における各種の意思決定の場への学生参加という2つが挙げられる。なお、必須的・発展的を問わず、「サービス利用者」に関する、教育の運営及び実施におけるあらゆるプロセス等への彼/彼女らの参加や関与を求めるすべての基準が未充足の場合が多いと判断せざるを得ない。
最後に、『専門職』の領域においては、前半の基準がよく満たされていると考えてよいが、後半の「公平性と多様性」における4つの必須的基準と1つの発展的基準(計5基準)と、「人権と社会的、経済的、環境的な正義」における3つの必須的基準と3つの発展的基準(計6基準)は、まだまだ検討の余地がある。特に、後者において、環境的な正義や植民地支配の影響、先住民ソーシャルワーカーに関する基準に関する日本の現状は不十分な点も数多く残る。 以上から、今後の社会福祉教育及びその研究の課題設定においては、多様性、環境問題を含むグローバルな課題、教育課程の運営や実習を含む様々な意思決定プロセスへの当事者(利用者)及び学生の参加と包摂、実習範囲の時間的・空間的な拡大(時間数、海外配属など)、環境的な正義などのようなキーワードが浮き彫りになっている。