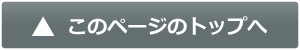アポリア連載
ニュースレター45号より、「アポリア連載」が始まりました。
「アポリア連載」は、会員の皆さまが、本学会の研究対象は「高等教育における社会福祉専門教育」という認識のもと、さまざまな高等教育機関から社会福祉教育のあり方を考えるきっかけとなれば、という想いより本連載を始めました。
第4回目は、本学会理事である白川充会員(仙台白百合女子大学)です。
大学教育を考える
日本社会福祉教育学会 副会長 白川 充
(仙台白百合女子大学)

「アポリア連載」の意図は、担当者によれば「本学会の研究対象である『高等教育おける社会福祉専門教育』という認識のもと、学会員が社会福祉教育のあり方を考えるきっかけにしたい」とのことである。ならば「大学教育を考える」という視点から、そのきっかけになる『材料』を提示してみたい。
恩師である米本秀仁先生が亡くなって1年半が過ぎた。本学会による米本先生追悼企画の中で、私は「米本秀仁先生のコア・カリキュラム研究への貢献」について執筆した。対象となる「コア・カリキュラム研究」とは、ソ教連の前身である日本社会福祉教育学校連盟が2003年から2013年まで取り組んだものが中心で、米本先生は社会福祉専門教育委員会の委員長(以下、米本委員会とする)を務め、私は委員会のメンバーの一人として参画した。あれから10数年がたった今、当時の議論や論点が、どのような意味があるのかを問うことは、それこそ議論が必要だか、その一部を紹介する。
当初、米本委員会ではふたつのコア・カリキュラムを構想していた。それが最終段階において一本化されることになる。ふたつのコア・カリキュラムとは、「社会福祉学コア・カリキュラム(6項目)」と「社会福祉専門職養成におけるコア・カリキュラム(Ⅴ群13項目)」である。米本委員会としては、社会福祉学と社会福祉専門職養成のコア・カリキュラムは関連こそするが、その構造と中身は違うものであるという認識であった。それが2010年の最終案では、この両者は統合され「社会福祉学を基礎とするソーシャルワーク教育のコア・カリキュラム」となったのである(その背景や経緯については、ここでは触れないが)。
このコア・カリキュラム構想の議論はその後、収束していくことになる。そして気が付けば、社会福祉士養成等の指定科目群が幅を利かせ、一方で、この指定科目だけでよいのか、という議論が一般化しているようである。
米本先生は、2012年3月、定年退職を前に日本社会福祉教育学会・第2回春季研究委集会において基調講演を行い、その中で「遺産相続」という項目を立て以下のように述べている。
「学校連盟の社会福祉専門教育委員会は当初、社会福祉学のコア・カリキュラムと専門職養成教育のコア・カリキュラムの二本立てで行こうとしましたが、『社会福祉学を基礎とするソーシャルワーク教育』というスローガンで一本化したのがⅥ群18項目です。これは実は社会福祉学とは何かという未決の問いがありながら社会福祉学を復権させることになるのかどうか。コア・カリキュラムの内容自体が同様なものとして設計されているのかという問題とも関連して、これなどはまだ議論は続くのではないか」(傍点筆者)と。
(出典:米本秀仁(2013)「社会福祉教育研究の回顧と展望-福祉系学会における教育研究と専門職養成教育の課題-」『日本社会福祉教育学会誌』(日本社会福祉教育学会)5-25.)

さて、その後、社会福祉学とは何かという未決の問題、関連するコア・カリキュラムの内容と設計に関する議論は続いたのであろうか。改めて問いたいことは、「高等教育における社会福祉専門教育」あるいは「大学教育を考える」上で、社会福祉専門教育には「コア・カリキュラム」は不要なのかということである。この問題(アポリア?)は、本学会の研究対象である『高等教育おける社会福祉専門教育』という認識のもと、大学教育を考える『材料』になるのではないだろうか。