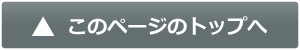専門教育とは「〇〇〇」である!
ニュースレター45号より始まった「専門教育とは、「〇〇〇」である!」は、実践者・研究者、各々の立場で「専門教育」について考えるきっかけとなれば…という思いより、スタートしました。
若手研究の方や現場実践の方を中心に、その人自身が考える「専門教育」とは何であるのかを「〇〇〇」という一言で表現してもらい、その理由(何を以て専門教育としているのかなど)などを教えていただく内容です。
第4回目は、星野 由利子会員(札幌麻生脳神経外科病院)、松原 正裕会員(日本メディカル福祉専門学校)のお二方の熱い想いをお届けします!
専門教育とは、「進化」である!
星野 由利子(札幌麻生脳神経外科病院)
<はじめに>
私は、医療現場のソーシャルワーカーとして、もうすぐ実践(歴?)40年を迎える。振り返ると学生の時代からソーシャルワーカーを目指し、卒業後もずっと「ソーシャルワークとは何か」を追求してきた。それは、勿論、一人では難しく教育機関の諸先生方や仲間のソーシャルワーカー達と、ある時は専門書を講読する勉強会として、またある時は調査研究や実習事業、研修事業を展開することを通してソーシャルワーク実践の面白さを味わってきたと思う。
そういう取組をこれまで続けてこられたことについて、関係者の皆様にはこの場をお借りし感謝申し上げたい。
<専門教育とは>
さて、今回、私に与えられた宿題は「専門教育とは」であるが、専門教育とはその領域を進化させる媒体と考えるので、端的に言うと「専門教育とは進化」ということになる。
フィールドが医療現場であることから、当然、他の専門職種を意識しその教育の違いを比較してきた。たとえば、医師。2018年に新専門医制度が導入され、大学を卒業し2年間の初期臨床研修後、診療科を選び3~5年間の専門研修を経て専門医試験を受け専門医資格を取得。原則5年ごとに更新審査を受け、医療の進歩を学び、実践を積むことが求められている。
私達ソーシャルワーカーも、実習カリキュラムが刷新され、現場に出た後には認定制度が導入されたことにより、本人が求めれば以前より研鑽を積む機会が増えた。また身近な例では、北海道で導入された「実習前OSCE」は、実習生の観察や判断、行動を導入前よりも実践的にしたし、現場のソーシャルワーカーを外部評価者としてシステムに加えたことで教育と実践の融合が生まれた。
<ある日の出来事>
今年3月に開催された日本脳卒中学会で、ある脳外科医から科研費で相談窓口の連携や就労支援、ACPなどに関して全国調査を実施し、そのデータを基にソーシャルワーカーや看護師・リハビリなどの専門職種を組織化し働きかけをしている姿を目の当たりにした。ソーシャルワークはソーシャルワーカーだけのものではないことに今更ながらショックを受けたが、逆にいろいろな専門職の実践の中でソーシャルワークが進化を早めるかもしれない。
その後6月、北海道医療ソーシャルワーク学会で、シンポジストとして招かれた訪問診療医達が訪問診療にソーシャルワーカー配置は必要だと述べる中、フォロアーの別の訪問診療医から「自分はソーシャルワーカーは雇わない。自分がソーシャルワークをしているので。」との発言があった。勿論、それに対し沢山の反論はあったが、残念ながら訪問診療領域のソーシャルワーカー配置についてその存在意義を証明するデータや根拠は示されず今後の課題となった。そんな中でも興味深かったのは、フロアーにいた社会福祉士資格を取得した医師の発言だった。その医師は、自身は訪問診療領域でソーシャルワーカーは必要と考えていることやこれからそれを証明したいと述べた。
なぜ、このような例に出会うのか。彼らが学ぶ医学には大きく分けて「基礎医学」、「臨床医学」、「社会医学」の3つの分野がある。注目するのは「社会医学」で、個人だけでなく、地域社会や集団全体の健康と福祉の向上を目的とする医学として、社会システムや環境といったマクロな視点から健康問題に取り組む点が特徴とされている。こういう教育を受けているのなら、これらの例も少し納得できる。
<ソーシャルワークを進化させるもの>
医療現場はコロナ禍を経て、人材不足、物価高騰など急速な変化から、将来的に病院は減り人々の生老病死も地域へと移り変わろうとしている。他の社会福祉の現場も、同じような困難を抱えている。この社会の変化に対し、実践現場と専門教育の交互作用がソーシャルワークの進化を加速させるのだと思うしそうあって欲しいと願う。

専門教育とは、「学生の多様な経験を教育資源として最大限に活用すること」である!
松原 正裕(日本メディカル福祉専門学校)
はじめに
私は母子生活支援施設や救護施設の相談員として従事したのち、現在は日本メディカル福祉専門学校で教員をしている。当校は一般養成施設に該当し、昼間1年間のカリキュラムで資格取得を目指す特性がある。社会福祉士を育成するための専門教育とは、いかなるものであるべきか。特に、大学卒業者や社会人経験者など、多様な背景を持つ学生が短期間で集中的に学ぶ「一般養成施設」においては、その教育のあり方が常に問われている。本稿では、養成教育の質の保証と実習のあり方と一般養成施設ならではの特性を踏まえ、専門教育について考えていきたい。
1. 社会福祉士養成教育が直面する現代的課題
第一に、「教育の質の保証と社会の変化への対応」である。2021年度から新カリキュラムが施行されたが、その教育内容が、複雑化・複合化する現代社会の課題に対応しうる専門職の育成に結びついているか、常に検証が求められる。単に国家試験に合格するための知識の詰め込みに陥ることなく、卒業生が専門職としてのコンピテンシー(実践能力)を確実に身につけられるような教育のスタンダードをいかに構築し、保証していくかが問われている。デジタル化の進展に対応したICT活用能力や、多職種・多機関と連携・協働するためのコミュニケーション能力、地域共生社会に向けた分野を横断的に学ぶ力など、新たな能力の育成も急務である。養成校は、教育内容や方法を自己点検・評価し、継続的に改善していく責務を負っている。
第二に、「ソーシャルワーク実践の根幹をなすソーシャルワーク実習の質の確保」という課題である。実習は、教室での学びを実践と結びつけ、ソーシャルワーカーとしての価値・倫理、知識、技術を統合する上で不可欠な機会である。しかし、実習先の確保難、実習指導者の負担増、そして実習内容の質のばらつきなど、多くの課題を抱えている。特に2か所実習となったことにより、ミクロ・メゾ・マクロの視点を学び得ることで、対人援助の機微を学び、専門職としてのアイデンティティを形成する上で、その効果と限界については慎重な検討が必要である。実習スーパービジョン体制を強化し、学生が実践を深くリフレクション(振り返り)できる環境を保障することが、実習の学びを最大化する鍵となる。これらの課題は、全ての養成校に共通するものであるが、特に一般養成施設においては、その教育の特性と深く関わってくる。
2. 一般養成施設における専門教育の特性と可能性
本校のような専門学校の社会福祉士科(一般養成施設)は、4年制大学の福祉系学部とは異なるいくつかの特性を持つ。それは、①多様なバックグラウンドを持つ学生層、②1年という短期集中型のカリキュラム、そして③国家試験合格という明確な目標設定である。これらの特性は、専門教育における課題であると同時に、大きな可能性を秘めている。
(1)多様な学生層という資源の活用

一般養成施設の学生は、新卒者だけでなく、様々な職種を経験した社会人、子育てを終えた主婦など、年齢も人生経験も実に多様である。この多様性は、専門教育における最大の資源となりうる。例えば、金融、IT、医療、教育、製造業など、異なる業界で培われた経験や視点は、福祉の課題を多角的に捉える上で非常に有効である。授業において、彼らの経験を題材とした事例検討やグループワークを行うことで、学びはより実践的で深みのあるものになる。学生同士が互いの経験から学び合うピア・ラーニングは、多様な価値観を理解し、コミュニケーション能力を磨く絶好の機会となる。教員は、ファシリテーターとして学生たちの経験知を引き出し、それをソーシャルワークの理論や価値と結びつける。あるいは、当校に入学し福祉を学ぼうとする思いを、ソーシャルワークの理論や価値と結びつける役割を担うことが重要である。
(2)短期集中型教育における専門性の深化
1年という短い期間で専門職を育成することは、確かに挑戦的な課題である。知識や技術が断片的な習得に終わり、専門職としての価値・倫理観が十分に内面化されないリスクは常にある。この課題に対し、一般養成施設は、カリキュラムの密度と効率性を極限まで高める工夫が求められる。

重要なのは、単なる情報の伝達ではなく、「ソーシャルワーカーとしての思考様式」を涵養することである。そのためには、講義、演習、実習の有機的な連携が不可欠となる。当校の実習は、7~8月に12日間、9~10月に8日間、2~3月に12日間の合計3回実施している。これをふまえると、講義で学んだ理論(ストレングス視点、エンパワメントなど)を、直後の演習で具体的な事例を用いてロールプレイングし、さらに実習で実践してみる。そして、実習での経験や葛藤を再び教室に持ち帰り、教員や仲間と共にリフレクションを行う。この「実践→省察→理論化→再実践」というサイクルを短期間に何度も繰り返すことで、知識は生きた知恵となり、ソーシャルワーカーとしての専門的アイデンティティが形成されていく。
(3)国家試験を越えた専門教育の追求
国家試験合格が学生と学校にとって大きな目標であることは事実である。しかし、専門教育が試験対策に終始してはならない。一般養成施設という特性上、学生は資格取得後に社会福祉の世界に飛び込む。本来、国家試験で問われる知識は、専門職として実践を行う上での最低限の基礎である。私たちの使命は、試験の合格ラインを越え、その先にある複雑な実践現場で活躍できる専門職を育成することにある。
そのためには、前述した現代的課題、すなわち「地域共生社会の実現」「多職種連携」「ICTの活用」といったテーマを、日々の授業に積極的に取り入れる必要がある。例えば、地域のNPOや当事者団体と連携したPBL(Project Based Learning:課題解決型学習)を導入することで、学生はよりリアルな社会課題に触れることができる。このような主体的な学びを通して培われた実践力や応用力こそ、国家試験の先にある専門職としてのキャリアを支える土台となる。
結論:未来を拓く社会福祉士専門教育を目指して
社会福祉士の専門教育とは、単に知識と技術を伝達する行為ではない。それは、複雑な社会の現実と向き合い、人々の尊厳を守るという揺るぎない価値・倫理観を基盤に、科学的根拠に基づいた思考と創造的な実践を展開できる専門家を育成する、知的かつ倫理的な営みである。 一般養成施設は、多様な人生経験を持つ人々を社会福祉の現場へと送り出すという、社会的に極めて重要な役割を担っている。その短期集中型という特性は、効率的な知識習得を可能にする一方で、いかにして深い専門性を醸成するかという問いを常に我々に突きつける。この問いに対する答えは、学生の多様な経験を教育資源として最大限に活用し、講義・演習・実習を有機的に連携させ、リフレクションを中核に据えた実践的な学びのサイクルを構築することにある。