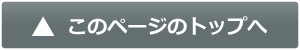生成AIを“うのみにしない”ためのAIリテラシー
日時
2026年3月29日(日)13:00~
会場
関西学院大学梅田キャンパス 1001教室https://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access/
講師
川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部
開催概要
生成AIの「もっともらしい誤り」を実際に体験し、適切な活用に視点を学ぶことを目的としています。講義(前半)とスマホやパソコンを用いてのワークショップ(後半)を予定しています。
スケジュール
詳細が決まり次第、お知らせします。
参加申し込み
参加申込〆切:2026年3月22日(日)までhttps://forms.gle/fWE9Hv4yqRmJPFsw8
チラシダウンロード
第16回春季研究集会チラシPDF
2026年1月31日(土)にアジア国際社会福祉研究所が主催する第10回国際学術フォーラムが開催されます。
本会も後援団体として,会員の皆様へお知らせいたします。
詳細は,下記リンクよりご確認ください。
第10回国際学術フォーラム
「世界に拓かれる仏教ソーシャルワークの可能性―理論と実践をつなぐスピリチュアリティの視点」
開催日:2026年1月31日(土) 10:00~16:30
開催のご案内 | 淑徳大学https://www.shukutoku.ac.jp/news/nid00005843.html
実践力を備えた専門職を養成する―個別性・多様性に着目した教育方法を模索する― 大会開催日程
2025年9月6日(土)~9月7日(日)
会場
川崎医療福祉大学(岡山県倉敷市松島288 山陽本線中庄駅から2キロ)
趣旨
2021年度から開始された社会福祉士養成新カリキュラムが5年目を迎えました.本学会では,実習・演習を中心に,教育のあり方について検討が重ねられてきました.人々を取り巻く課題が複雑化・複合化・深刻化・グローバル化と多様化していく中で,ソーシャルワーカーは多様な地域住民を支え共に活動することが求められます. そして,社会福祉教育においても多様な学生への教育が求められます.ICT(情報通信技術)やAI(人工知能)などの情報伝達技術が発展する反面,顔と顔を合わすコミュニケーションにおける課題が指摘されることが少なくありません.
第21回大会では,個別性・多様性に着目した教育をテーマに取り上げます.ソーシャルワーカーの基本的技術である「伝える」を手がかりにスーパービジョンを再考し,地域における実践型教育を検討します.参加者の皆さまと共に,“多様な”側面から,社会福祉教育を考える機会にできればと考えています.
スケジュール
9月6日(土)
13:00~13:15 【開会式】 13:15~15:15 【基調講演】 15:30~17:20 【開催校企画シンポジウム】 17:50~19:50 【情報交換会】
9月7日(日)
10:00~12:10 【学会企画シンポジウム】 12:20~13:00 総会 13:00~14:00 昼食休憩 14:00~14:25 【教育実践報告】 14:30~15:30 【自由研究報告】 15:30~ 【閉会式】
プログラム内容
【基調講演】 9月6日(土)
「伝えたいことを・伝わるように・伝える―TEACCHの考え方を援用した指導―」
趣旨
自閉症・発達障害者への支援であるTEACCH(Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children)プログラムは,世界で一定の評価を得ている.TEACCHの特徴を自閉症・発達障害者以外の人々にも援用し活用することで,コミュニケーションを円滑に進めることができる.正確・適切に共有するための具体的方法について,TEACCHの考え方から社会福祉教育への示唆を得る.
「TEACCHの考え方の基本」川崎医療福祉大学 准教授 諏訪利明
「TEACCHの考え方を実践で活用する」川崎医療福祉大学 講師 小田桐早苗
【開催校企画シンポジウム】 9月6日(土)
「現場にスーバービジョンはあるのか?―“四者良し”を目指すスーパービジョン―」
趣旨
実習指導におけるスーパービジョンの重要性は指摘されているものの,ソーシャルワーク実習はもちろん現場において,スーパービジョンが浸透しているとは言い難い状況がある.今回のシンポジウムでは,特に実習に着目して学生へのスーパービジョンについて検討したい.
伝えたいことを・伝わるように・伝えるスーパービジョンとは,クライエントの利益を視野に入れたスーパービジョンとは,実習指導者,実習担当教員,そして実習生だった立場から,実習スーパービジョンについて検討する.
コーディネーター:竹中麻由美(川崎医療福祉大学)
話題提供(実習スーパービジョンを巡る動向)及びコメンテーター:楢木博之(静岡福祉大学)
シンポジスト:
【学会企画シンポジウム】 9月7日(日)
「資格者養成教育の範囲を超える-社会・地域における実践型教育から学ぶ-」
趣旨
社会福祉士をはじめとする社会福祉専門職の養成は、法律をはじめ様々な規定に従って行われ、ある意味で「品質保証」が行われている。しかし、それは高等教育と連動して行われる場合、運転免許取得のための自動車学校のような完全に標準化された画一的品質保証とは異なる。最低限の標準的力量は備えながらも、各養成校の理念・目的に応じた工夫・実践が行われている。その中でも、社会・地域と触れ合う参加型のカリキュラムには各校・各教員の多様な工夫がみられており、本学会としても共有し会員の学びとする価値は高いと考えられる。
今回は以下の要件を満たす科目を選び報告を依頼した。
社会福祉士等資格養成科目ではない
社会・地域に学生が積極的にかつ主体的にかかわっている
ボランティア活動のようなものでなく担当教員が一定程度以上の関与をしている
以上の3要件である。
コーディネーター:小山隆(同志社大学)
シンポジストと科目:
【開催校企画ランチョンセミナー】 9月7日(日)
「指導する立場で知っておきたいイマドキ学生の生成AIの使い方」
趣旨
生成AIは教育・研究で活用されている.もちろん学生も例外ではない,いやむしろ学生の方が使いこなしているともいえる.学生を指導する立場となる教員や現場の職員が知っておきたい,イマドキ学生がどのように生成AIを使いこなしているのかを知る機会となる.
開催担当校及び共催
○主催:日本社会福祉教育学会
○共催:岡山県社会福祉士会(実習指導者養成研修委員会),ソーシャルワーク教育学校連盟中国四国ブロック(予定),岡山県医療ソーシャルワーカー協会(予定)
○開催担当校:川崎医療福祉大学 医療福祉学科
参加申込方法と参加費
※必ず「事前の参加登録」と「参加費のオンライン決済」をお願いします。
参加費
会員・非会員 学生・大学院生 全日参加 8,000円 2,000円 1日参加 4,000円 1,000円
申込締切と申込先
自由研究発表/教育実践報告の申込締切:8月7日(木)
参加申込締切:9月1日(月)
【教育実践報告と自由研究発表の分類】
自由研究発表:口頭発表
教育実践報告:ポスター掲示による発表
大会の参加申込と自由研究報告及び教育実践報告の発表申込は,下記リンク先学術集会JPで受け付けます。
第21回日本社会福祉教育学会|学術集会JPhttps://gakujutsushukai.jp/jsswe2025
お問い合わせ先
日本学術会議法案の修正について、当学会は2025年4月23日発出の日本社会福祉系学会連合による「日本学術会議法案に関する会長声明」への賛同を表明しております。
この度、法案の修正を求める社会学・社会福祉学・社会政策学研究者有志による「署名活動のホームページ」が開設されました。
署名への参加は各個人のご判断によるものですが、理事会の議を経て、サイト開設については広く周知することになりましたので、お知らせいたします。
「日本学術会議法案の修正を求める社会学・社会福祉学・社会政策学研究者有志ホームページ」
なお、署名活動は継続的に実施予定とのことですが、国会では4月25日(金)に続き5月7日(水)に審議が行われる予定のため、署名の印刷・郵送の手続きを考え、4月30日(水)正午にいったん集約される予定となっていますことを申し添えます。
日本社会福祉教育学会会長 志水 幸
日本社会福祉系学会連合より2025年4月23日に発出された「日本学術会議法案に関する会長声明 」へ賛同いたします。
日本社会福祉教育学会会長 志水 幸
学会誌第29・30合併号をお送りさせていただきました。
本号では、課題研究「ICTを活用した社会福祉教育のあり方に関する総合的研究」の成果がまとめられた3つの論文が特集論文として掲載されています。
この特集論文については、保正論文→大村論文→山田論文の順にお読みいただくことで理解しやすくなっておりますが、編集過程でのミスにより大村論文→保正論文→山田論文の順に掲載されてしまっています。
皆様のご理解の一助として、保正論文→大村論文→山田論文の順にお読みいただくことをお勧めいたします。
この度は編集過程でのミスがありましたこと、深くお詫び申し上げます。
学会誌編集委員会
2025年2月15日(土)にアジア国際社会福祉研究所が主催する第9回国際学術フォーラムが開催されます。
本会も後援団体として,会員の皆様へお知らせいたします。
詳細は,下記リンクよりご確認ください。
第9回国際学術フォーラム
仏教ソーシャルワーク探求の旅、その先へ ~なぜ世界は仏教ソーシャルワークを無視できないのか~
開催日:2025年2月15日(土)
開催のご案内 | 淑徳大学https://www.shukutoku.ac.jp/news/nid00004685.html
第9回国際学術フォーラムチラシPDF
社会福祉士養成新カリキュラムにおける2ヶ所・240時間実習実施に関する課題解決に向けて
日時
2025年3月16日(日)13:00〜15:30
開催方法
オンライン開催
開催趣旨
日本社会福祉教育学会では、新カリキュラムが本格導入された2022年度から2024年度までの期間、継続的に2カ所・240時間実習の実施に関連するシンポジウムやワークショップを行なってきた。第12回の春季研究集会では、基調講演とシンポジウムを開催、第19回大会では開催校主催でワークショップを実施、更に第14回春季研究集会において再度ワークショップを開催した。
これらの継続的な集まりに参加された皆さんから出されたものをまとめると、実習実施にあたり、異なる2カ所の実習をどのようにつなぐのか、異なる2カ所目の実習先との連携のあり方、実習先・養成校・実習生それぞれへの負担増にどのように対応すべきか、という3つの課題に集約される結果となり、第20回大会(2024年9月)で報告のポスターを掲出した。
今回の春季研究集会では、2カ所実習として継続してきたテーマの総まとめ的な意味で、特色ある方法で実習を実施しておられる養成校から実施報告をしていただき、更に各校の工夫などを出し合って上記の3つの課題への対応を話し合う機会を設けたいと考えている。すでに2カ所実習が2年目を終えた養成校が多いと思われるので、それぞれの経験からアイディアを持ち寄り、今後のより良い2カ所実習へとつながっていくことをめざしたい。
参加申し込み
参加申込〆切:2025年3月7日(金)までhttps://forms.gle/XXH2jfwVRYFXUzYu8
プログラム
13:00 開会 13:10 各養成校からの実施報告 14:10 休憩 14:20 登壇者及び参加者によるディスカッション 15:00 各グループからの報告 15:30 閉会
チラシダウンロード
第15回春季研究集会チラシPDF
訃報
本学会の名誉会員である岡本民夫先生が、2024年12月11日(水)に満88歳でご逝去されました。
先生は2008年から2014年まで監事を務められるなど、長年にわたり本学会の発展のために大きな貢献を果たされました。ここに謹んでご冥福をお祈りします。
本学会では、『日本社会福祉教育学会誌(Japanese Journal for the Study of Social Welfare Education)』第32号(2025年9月発行予定)への投稿論文を募集しています。editor.jsswe@gmail.com (日本社会福祉教育学会誌編集委員会宛)
本学会では、『日本社会福祉教育学会誌(Japanese Journal for the Study of Social Welfare Education)』第32号(2025年9月発行予定)への投稿論文を募集しています。editor.jsswe@gmail.com (日本社会福祉教育学会誌編集委員会宛)
自由研究発表登録,事前参加申込方法を掲載しました。
皆様のご参加,研究発表をお待ちしております。
第20回大会ページ
SDGsと社会福祉教育 大会開催日程
2024年9月7日(土)8日(日)
会場
1日日
八王子市学園都市センター(JR八王子駅北口正面イベントホール)
2日目
創価大学・中央教育棟
大会スケジュール
1日目(9月7日) 学園都市センター
13:00~13:15 開会式 13:15~14:45 基調講演 14:45~15:00 休憩 15:00~16:40 開催校企画シンポジウム 17:00~17:30 休憩・移動 17:30~19:30 情報交換会
2日目(9月8日) 創価大学 10:00~12:30 学会企画シンポジウム 12:30~12:40 休憩 12:40~13:15 総会 13:15~14:00 昼食休憩 14:00~14:25 新カリ2か所実習に関する情報交換 14:25~15:25 自由研究報告 15:25~15:30 閉会
プログラム
基調講演・講師
「SDGsの実現に必要な社会福祉教育とは ~環境福祉学の視点から~」(仮)
開催校企画シンポジウム
「SDGsに貢献する地域課題解決型の教育活動の取り組みと社会福祉教育 ~循環する地域参加と学び~」(仮)
【趣旨説明】
地球沸騰化や日本少子高齢化、格差社会等による社会課題はより身近になっている。大学では地域貢献が第三の使命といわれる。法学部での夜回り、経営学部での子ども食堂の運営。今、社会福祉以外の学部やゼミで社会課題に取り組む活動が増えている。また、2022年から、高校では本格的に探究学習がスタートした。探求学習では自分なりに問いを立て、情報を集めて分析して、まとめ発表する一連の流れを行われてくる中で、これらを受けて社会課題を取り扱い、考えアクションに結び付ける流れをうけて高等教育機関ではこれらをさらに展開するような活動の提供はないのだろうか。
活動を通して課題の発見では社会福祉学部ではこれらは無関係なのだろうか。本学で地域課題に取り組むゼミ・教員の活動をもとに、社会福祉学以外の領域での地域課題への取り組みそしてその教育に対する考えなどから地域課題の解決、地域参加への在り方を検討する。これらは、グローバル定義においても『ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として・・・諸科学の』とあるように別領域の知識・技術をもって地域課題の解決に取り組む広域の知識を取り込む方策への一助となると考える。
司会
シンポジスト
伊藤 貴雄 氏(文学部教授)
コメンテーター
学会企画シンポジウム
テーマ
「メゾ及びマクロ・レベルの力量を身につけるための循環型教育 ~ソーシャルワーク実習における学校と実習先の協働に焦点を当てて~」(仮)
【趣旨説明】
新しい養成カリキュラムにおいては、地域共生社会の実現に向けたソーシャルワーク機能を果たせる力、とりわけ分野横断的な実践力や住民と協働する実践力の習得への期待が高い。地域における多様なニーズや多機関協働、社会資源開発などの実態をより深く学ぶために、ソーシャルワーク実習の充実化が図られている。具体的には、実習時間が拡大され、機能の異なる2か所以上の実習先への配属が行われるようになってきた。また、実習のねらいと内容については、「地域」が一つのキーワードとなり、メゾ及びマクロ・レベルの力量を身につけられる実習教育が求められている。
このような実習を行うためには、学校と実習先の連携による循環型教育が欠かせない。このシンポジウムでは、メゾ及びマクロ・レベルの実践力を習得できる実習に先駆的に取り組んでいる学校及び実習先の教育枠組みと教育実践について取り上げ、今後の可能性と課題について検討する。
全体司会・コーディネーター
報告1
報告2
モデレーター
自由研究発表
下記リンク先学術集会JPよりご登録ください。
学術集会JP|第20回日本社会福祉教育学会https://gakujutsushukai.jp/jsswe2024
発表登録〆切:7/17(水)
大会参加申込
※会員,一般,学生の方々と八王子市民向けの参加申込は方法が異なりますのでご注意ください。
【八王子市民の方のお申込み】
1日目のプログラムのみ,八王子市民の皆様は無料でご参加いただけます。
第20回大会八王子市民向け参加申込フォームhttps://forms.gle/mgS9ZjxqMnAkugJ79
八王子市民の方でも2日目のプログラムへの参加(有料)をご希望される場合は,下記,会員,一般,学生向け参加申込のリンク先からお申込みください。
【会員,一般,学生の方のお申込み】
下記リンク先,学術集会JPよりお申込みください。
学術集会JP|第20回日本社会福祉教育学会https://gakujutsushukai.jp/jsswe2024
事前参加申込〆切:8/25(日)
お問い合わせ先
本学会では、『日本社会福祉教育学会誌(Japanese Journal for the Study of Social Welfare Education)』第31号(2025年3月発行予定)への投稿論文を募集しています。editor.jsswe@gmail.com (日本社会福祉教育学会誌編集委員会宛)